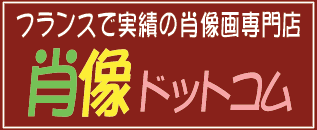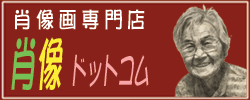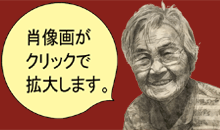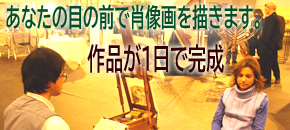- トップ
- エッセイ
- No.22 アンナ・クレーフェの肖像画
メールマガジン形式
時空を超えて~歴代肖像画1千年 No.0022
2013年07月24日発行
★歴史上の人物に会いたい!⇒過去に遡り歴史の主人公と邂逅する。 そんな夢を可能にするのが肖像画です。
織田信長、武田信玄、豊臣秀吉、徳川家康、ジャンヌ・ダルク、モナリザ ……古今東西の肖像画を画家と一緒に読み解いてみませんか?
□□□□今回のラインナップ□□□□
【1】 ホルバイン作「アンナ・フォン・クレーフェの肖像画」(ルーブル美術館)
【2】 肖像画データファイル
【3】 像主について
【4】 作者について
【5】 肖像画の内容
【6】 次号予告
【7】 編集後記
◆◆【1】「アンナ・フォン・クレーフェの肖像画」◆◆
今回取り上げる作品はイギリス国王ヘンリー8世の妻としてドイツの小国か ら輿入れするアンナ・フォン・クレーフェ24才の肖像画です。
作者のハンス・ホルバインはドイツ・ルネサンスの最後を飾る画家で、史上 最高の肖像画家といわれています。
45才のとき不慮の死を遂げますが、これはその4年前に全身全霊を傾けて制 作に当たった作品でした。
さて大男で精力絶倫のヘンリー8世は順番に6人の妻を迎えるのですが、ホル バインは宮廷画家としてその内の4人を描いています。
これに、他の宮廷画家の手になる作品を加えて、勢揃いした「ヘンリー8世 と6人の妻」の肖像画もご覧下さい。
★ホルバイン作「アンナ・フォン・クレーフェの肖像画」はこちら
⇒ https://www.shouzou.com/mag/p22.html
◆◆【2】肖像画データファイル◆◆
作品名: アンナ・フォン・クレーフェの肖像画
作者名: ハンス・ホルバイン
材 質: テンペラ(羊皮紙)
寸 法: 65×48cm
制作年: 1539年
所在地: ルーブル美術館(パリ)
注文者: イギリス国王ヘンリー8世
意 味: 寡夫となったヘンリー8世の花嫁探しは海を越えることになった。
短気な王は品定めのために自らの渡海を望んだのだが、相手は王族であり さすがにこれははばかられた。
王の信頼厚い宮廷画家ホルバインは特使に随行し、各地で花嫁候補の肖像 画を制作した。中世版のお見合い写真である。
その中の一つである本作品はヘンリーの気に入るところとなり、彼女を4番 目の正妻として迎えるのである。
肖像画・油絵の注文制作 肖像ドットコム https://www.shouzou.com/
◆◆【3】像主 アンナ・フォン・クレーフェ(1515-57)について◆◆
1.アンナの生い立ち
アンナ・フォン・クレーフェは、1515年9月22日、オランダ国境に接するド イツ西部のクレーフェ公国の王女として誕生した。
父はクレーフェ公国のヨハン3世で、母は近隣のユーリヒ・ベルク公国の相 続人マリアであり、二人が結婚した結果、両国は1521年に統合され、クレーフ ェ・ユーリヒ・ベルク公国となった。首都はデュッセルドルフである。
アンナは4人兄弟の次女で、3つ年上の姉ジビラ、1つ年下の弟ヴィルヘルム そして2つ年下の妹アメリアがいた。
父親は、教養豊かな人物で、神学に関心が深く、人道主義者・エラスムスの 影響を受けたプロテスタント寄りのリベラリストだった。また、息子のヴィル ヘルムの教育には非常に熱心だった。
一方、母親は厳格なカトリック教徒で、娘たちをいつも自分の目の届くとこ ろに置いていた。また当時のドイツでは、学問は女性に不要なものと考えられ ていたため、ジビラもアンナもアメリアも母国語しか話せなかった。
また、高貴な女性がフランス人のように音楽や踊りをたしなむことは、非難 されるべき行為であり、厳しくしつけられたアンナの趣味はといえば裁縫だけ だった。
2.当時のヨーロッパの情勢
16世紀のヨーロッパは、宗教改革の嵐の吹き抜けた時代である。
1517年、ドイツの神学教授マルティン・ルター(1483-1546)が、カトリッ ク教会の免罪符販売を批判して大きな反響を呼ぶ。これに対してローマ教皇レ オ10世は1521年ルターを破門。
ドイツ国内では教会の腐敗に対する不満が高まっていたため、ルターを支持 する諸侯が団結し、プロテスタント(抗議者)となって宗教改革運動を推し進 めた。
カトリックとプロテスタントの対立は、次第にヨーロッパ全土に飛び火。
ルターを支持するドイツ国内のプロテスタント諸侯は、1530年になるとザク セン公を中心にシュマルカルデン同盟を結成した。
1530年代の国際情勢は、
(1)スペイン王を兼ねる神聖ローマ帝国皇帝カール5世が、1527年のローマ
略奪後ローマ教皇クレメンス7世を支配下におくカトリック勢力
(2)イタリア支配権をめぐってカール5世と対立するフランスのフランソワ
1世がプロテスタントのシュマルカルデン同盟と結んだ勢力
3.クレーフェの外交
こうした中、小国クレーフェ・ユーリヒ・ベルグ公国のヨハン3世は、リベ ラルな姿勢を貫く。シュマルカルデン同盟には参加しないが、ザクセン公に長 女ジビラを嫁がせることで、協調路線を敷いたのである。
その一方で、国境を接する神聖ローマ帝国のカール5世とは反目しあう状況 だったから、保身のためにイギリスと結ぶことは願ったりかなったりだった。 実現しなかったけれども、1530年には息子のヴィルヘルムとイギリスの王女 メアリーとの結婚を打診している。そして1537年に国王ヘンリー8世が王妃を 失ったことを知るとヨハン3世は娘との縁談をもちかけた。
1539年にヨハン3世は亡くなったが、息子のヴィルヘルムが即位し、アンナ 姉妹の結婚話も継承された。
4.イギリス国王ヘンリー8世(1491-1547)とは
ヘンリー8世は、父ヘンリー7世が創設したイギリスチューダー朝(1485- 1603)2代目の国王である。
暴君であり、破壊者であり、青ひげとも呼ばれる。いかなる意味でも偉大な 君主ではなかったが、3代目のエドワード6世、5代目のメアリー1世、6代目の エリザベス1世を生んだ。
(1)皇太子ではなかった次男のヘンリーは、当初、詩人である家庭教師から 比較的自由で情操豊かな教育をうけた。そのため芸術家肌の人間に育つが、移 り気でわがまま、図体と野心だけが大きな男であった。
十代の彼は万能の天才と称される。1メートル84センチの巨漢ながら、やせ 面でハンサム。フランス語、ラテン語を話し、イタリア語も解する。乗馬や投 げ矢、弓は誰よりも勝った。
音楽はほとんどの楽器を弾け、楽譜を見て歌うこともできた。彼の作曲した 音楽も伝わっている。
(2)ランカスター家の末席に連なる貴族であった父・7世の周囲には、彼に取 って代わろうという前王朝プランタジネット朝の王位継承者が多数おり、いか に彼らを除くかが、8世にとっても重大な問題だった。
1509年の父の死後、18才で即位したヘンリー8世は、政敵に対して過酷に臨 み処刑された有力者や名家の人々は50名を超える。多くの有能な側近にも恵ま れたが、いかに勲功を重ねようと、意に沿わなければ即座に処断された。
中でも大法官として宰相の職務を担ったトーマス・ウルジー(1475-1530) トーマス・モア(1478-1535)、トーマス・クロムウェル(1485-1540)の三ト ーマスはいずれも大逆罪に問われ、病死・或いは断頭台送りとなった。
(3)戦争を忌避し外交を優先した父とは異なり、野心的なヘンリー8世は、対 仏百年戦争の結果失われたフランス国内の領土を奪還すべく、大陸にたびたび 出兵した。同時にフランスと同盟するスコットランドとも戦争を繰り返した。
しかし、ヘンリーに軍事的才能はなく、戦争による多大な出費によって国家 財政は火の車となった。
また父ヘンリー7世の庇護の下で、北米大陸を発見したのはイタリア人探検 家カボット親子だったが、先見性を欠いたヘンリー8世の代になると財政難の ため援助は打ち切られた。
(4)ヘンリー8世について最も有名な話はその結婚と離婚である。
最初の結婚は即位の年で、相手はスペイン人、キャサリン・オブ・アラゴン (1485-1536;カタリーナ・デ・アラゴン)。実兄アーサーの妻で、結婚後半 年で夫を亡くしていた。
ヘンリー8世の最初の妻となったキャサリンは、7回の出産を通して娘メアリ ー(のちの女王メアリー1世)を産む。しかし、男児が育つことはなかった。
ヘンリーは妻のたび重なる妊娠期間中に愛人を作り、キャサリンの侍女エリ ザベス・ブラントとの間には男児をもうけている。
他にも、エティエット・ラ・ボーム、メアリー・ブーリン、マッジ・シェル トン、アン・ヘイスティングズ、ジェイン・ホピクールト、ジョアン・ドブス ン、メアリー・バークリーという名前が伝わっている。
未だ安定していないチューダー朝の2代目として、男の跡継ぎを作ることが 悲願だったヘンリー8世は、1526年キャサリンの侍女アン・ブーリン(1501- 36)と恋に落ちた。かつての愛人メアリー・ブーリンの妹である。
彼女の父トーマス・ブーリンは有能な外交官。母エリザベスはノーフォーク 公爵の妹である。ブルゴーニュの宮廷に続きフランスの宮廷にも出仕していた アン・ブーリンはフランス仕込みの典雅なマナーと駆け引きに長じていた。
ヘンリー8世はアンと結婚するために、妻を離縁することにした。
これが史上最大の離婚と呼ばれることになる。
カトリックの教えでは禁じられていた離婚だが、ローマ教皇の許可があれば 事実上は可能である。しかし、当時教皇クレメンス7世は神聖ローマ帝国皇帝 カール5世の権力下にあった。
カール5世はスペイン王カルロス1世も兼ねており、彼の母親ファナはキャサ リンの実姉。キャサリン側に立つ甥のカールは、クレメンスに圧力をかけ、 離婚を許可させなかった。
折りしも宗教改革の嵐が吹き荒れる中、ヘンリー8世はキャサリンとの離婚 を断行するために、ローマ教会と絶縁することを決定。代わりに独自にイギ リス国教会を立ち上げる。
彼はローマ教会への上告禁止法(1533年)、国王を国教会の唯一の首長と する国王至上法(1534年)を相次いで制定。もはや神にも等しい権力を振り 回す。国内のカトリック修道院はすべて取り壊され、財産は没収された。
こうしてキャサリンとの24年間の結婚生活は無効とされた。
1533年、妊娠中のアン・ブーリンは晴れて2番目の妻の座に納まり、同年 女児(のちの女王エリザベス1世)を出産。あくまで離婚を認めないキャサリ ンは城に監禁された。
3年後の1536年、誇り高きスペイン王女キャサリンは貧困の中で病死した。 享年50。大陸では毒殺の噂が広まった。
しかし、大恋愛の末王妃の座におさまったアン・ブーリンさえも男児を産む ことができぬまま飽きられた。
アンの妊娠中に彼女の侍女ジェーン・シーモア(1508-37)に手をつけたヘ ンリー8世は、アンが流産すると姦通の罪を押し付け、ついにはロンドン塔で 斬首刑に処した。
3番目の妻となったジェーンは、翌1537年待望の男児(のちの国王エドワー ド6世)を出産するが、産褥熱のため12日後に死去。
まさに、最初の妻は2番目の妻に祟り、2番目の妻は3番目の妻に祟ったとし か思えない。さすがのヘンリー8世も此度の死別はこたえたようだったが、別 の意味で彼こそが張本人だったのだ。
ヘンリー8世は、対仏戦争の間にも現地の女性に手を出し、梅毒を患って いた。大航海時代の副産物として世界中に広まった梅毒は、彼の妻たちのあい つぐ死産、流産、虚弱児出産、産褥熱の原因と考えられている。
ともかくもアンナ・フォン・クレーフェが嫁ぐ予定のイギリス国王ヘンリー 8世とはこのような男であった。おまけにアン・ブーリンと出会った30代半ば からは熊のように肥満し始めていた。
5.アンナ・フォン・クレーフェの肖像画とライバルたち
1538年から39年にかけて、イギリス国王の宮廷画家は多忙な日々にあった。 国王の命でドーバー海峡を渡り、幾人もの、お妃候補の肖像画を描かかければ ならなかったからである。
1538年3月12日、ネーデルランド(現在のベルギー)のブリュッセルで、16 才の未亡人、デンマークのクリスティーナの肖像画を制作。
6月にはフランスのル・アーブルで、大貴族の娘ルイーズ・ド・ギーズと、 マルグリット・ド・ヴァンドームの肖像画を制作。
8月には再びフランスのジョワンヴィルで、ルネ・ド・ギーズを描く予定だ ったが、当人の拒否に遭う。次にナンシーで、従姉妹のアン・ド・ロレーヌ を描く。
1539年の7月8月になるとついに画家は、ユーリヒ=クレーフェ=ベルク公国 にやってきた。そしてアンナ王女とアメリア王女の姉妹を描いた。
肖像画家はドイツ人だったから母国語しか話せない姉妹も、意思の疎通に難 儀することはなかった。
肖像画を見たヘンリー8世の一番のお気に入りは、デンマークのクリスティ ーナである。前デンマーク王の父と、神聖ローマ帝国・皇帝カール5世の妹で ある母との間に生まれた彼女は、ミラノ公の未亡人で、評判の美女だった。
しかし、ことはヘンリーの思惑通りには進まず、長い時間をかけて何の進展 も見せぬまま破談となった。原因は政治的理由だけではなかった。イギリス国 王の行状は列強の間では、知らぬものがなかったようである。
伝えられた噂は、最初の外国人妻を離縁し、彼女が承諾しないとみるや毒殺 し、2番目の妻を無実の罪で断頭台送りにし、3番目の妻を出産後にろくに休ま せもせず死なせた、というものであった。
デンマークのクリスティーナは、イギリスの使者に対して、やんわりと 「私に首が二つありましたら是非」と言ったのだとか。
6.アンナの結婚
ヘンリー8世が次に魅せられたのはアンナ・フォン・クレーフェの肖像で ある。端正な容貌と華奢な体つき。英読みアン・オブ・クレーブ。24才。
あのアン・ブーリンと同じ名だが、論争好きで「雌ライオン」と呼ばれた 猛々しさは微塵もない。前妻ジェーン・シーモアと共通する穏やかさが感じ られた。
1539年10月にイギリスとクレーフェの間で結婚協定が調印された。
イギリス側では、上告禁止法や修道院解散など一連の法案の立役者トーマス ・クロムウェルこそが、この政略結婚の推進者だった。彼自身プロテスタント であり、ドイツのルター派と結ぶ外交政策を唱道していたからである。
12月31日に新婦アンナはイギリスに到着。4番目の妻との結婚式は1540年1月 に執り行われた。短気なヘンリー8世は婚礼に先立ってさっそくアンナに面会 しに行ったが、大いに失望したという。
新妻は、言葉が通じないのに加え音楽や文学の知識を持ち合わせていない。 ヘンリー好みの楽器を奏でたり、ゲームに興じるような、陽気さも華やかさも まったく欠いていた。
「上品であるが伝えられていたほどきれいではない」
初夜のあと国王はクロムウェルを口汚くののしった。興奮も欲望も起こらな い。背が高過ぎる。胸は垂れ下がり、肉はたるんでいる。それにこの鼻の高さ は何だ。
「フランドルの雌ロバを連れてきおって」
しかし4晩の間は出来る限りの努力をしたのだという。8日たってもヘンリー は床入れまで行くことができなかった。そしてお休みの挨拶とキスがこれに変 わった。
この件に関して花嫁アンナは、英語をまったく解せず、また母親の厳格なし つけと監視によって世俗のことには全く無知であったため、いかなる屈辱も感 じなかったそうである。
7.アンナの離婚
ヘンリー8世はアンナの侍女のキャサリン・ハワード(1521-1542)に目を付 けた。魅力的で小柄な18才の娘。名門ハワード家の出身であり、アン・ブーリ ンのいとこでもあった。男女経験は豊富で、恋の手管にも長けていたのだ。
一方のアンナはといえば、春から夏にかけて、言葉が少しずつ分かるように なり異国での生活が快適に思われ始めていた。
ところが6月になると王の使者とドイツ語通訳がやってきて、突然、結婚は無 効だったと告げられたのである。
アンナはひどいショックを受け無表情のままだったが、王の命にはおとなし く従った。従わなかった妻たちがどうなったのか知っていたがゆえに。
国王陛下にはいつでも喜んで従うと答え、差し出された文書の末尾に王妃の 文字を入れず「アンナ、クレーフェの娘」と署名した。
アンナの回答はヘンリーの最も喜ぶ内容のものだった。わがままな王もこう なると寛大になれるのである。
アンナは「王の妹」という地位に置かれ、さまざまな州の領地からなるかな りの不動産を与えられた。イギリスを離れない限り、これらの土地は終生アン ナのものとなる。
イギリスにとっては、クレーフェ公国との関係を悪化させないことが最重要 だったから、“この処遇はアンナ自らが望むものであり”、イギリスとの友好 関係を続けるよう促す旨の手紙を、ヴィルヘルム公宛に書き送らせている。
同月離婚は正式に承認され、そのニュースはヨーロッパ各国を駆け巡った。 フランス国王フランソワ1世は信じられないという顔つきで繰り返した。
「王妃とは今の王妃のことか?」
そうです、あの王妃ですと言われると、「あー」というため息をもらした。
冷徹な神聖ローマ帝国皇帝カール5世は、クレーフェとの関係が良くなる兆 しだと感じていた。
同年7月28日ヘンリー8世と5番目の妻キャサリン・ハワードとの結婚式が挙 行された。アンナ・フォン・クレーフェとの縁談を仕切った重臣トーマス・ク ロムウェルは、この日ロンドン塔で処刑された。
同じ頃、前王朝プランタジネット朝の生き残り、年老いたソールズベリー伯 爵夫人マーガレット(1473-1540)が大逆罪で処刑されている。彼女は、かつ てキャサリン・オブ・アラゴンに仕え、王女メアリの教育係でもあった。
ソールズベリー伯爵夫人の罪は事実無根だったから処刑の間際までもそれを 叫び続けた。それを後ろから断頭吏が遮二無二切りかかり、絶命するまで何度 も斧が振り下ろされたという悲惨な最期が伝わっている。
クロムウェルに代わって彼と対立していたノーフォーク公爵トーマス・ハワ ードの一族が上昇気流に乗る番と思われた。
孤独なアンナは思慮深く振舞った。またイギリスの人々からも好かれ始めて いた。ヘンリー8世の娘であるメアリーや幼いエリザベスとの仲もよく、かつ ての侍女であった新王妃にも敬意を払うことを厭わなかった。
こうした中で、1541年11月ノーフォーク公の姪であるにもかかわらず、あい かわらず身持ちの悪い王妃キャサリン・ハワードがとうとう逮捕された。姦通 の罪である。
ぶよぶよに太って両脚に潰瘍のできた50才のヘンリー8世は、もはや魅惑的 な若妻を満足させることができなくなっていたのである。
いとこのアン・ブーリンのときとは違って、罪状は疑いようがない。1542年 2月13日、21才のキャサリンはロンドン塔で斬首された。
8.その後のアンナ
ヘンリー8世も若い娘には懲りたのだろう。
1543年7月12日、52才のヘンリー8世と6番目の妻キャサリン・パー(1512- 1548)との結婚式が行われた。31才のキャサリン・パーは2度も夫を失った未 亡人であり、ヘンリーももはやその純潔を疑う必要がなかった。
キャサリン・パーについては誰一人美しいと述べている人はいない。
クレーフェの娘アンナは、今度こそ自分の出番だと思っていたのに、選ばれ たのはなんと自分より年上の婦人である。さすがの彼女も“自分ほどにもきれ いじゃない”と憤慨した。
キャサリン・パーは、あの3番目の妻ジェーン・シーモアの弟、トーマス・ シーモアの恋人だったが、再婚後は年老いた病身のヘンリーに対して献身的に 仕えた。
彼女は著作を残すほどの聡明な女性で、継子たちを愛し、彼らにふさわしい 教育環境を整えた。また夫に懇願して、メアリーやエリザベスの王位継承権を 復活させた。
3年後、自分の息のあるうちに、最後の有力者ノーフォーク公爵家を除こう としたヘンリー8世は、若い4代目のヘンリー・ハワードを逮捕・処刑。
斬首された二人の王妃の伯父である3代目のトーマス・ハワードも、ロンド ン塔に幽閉されていたが、処刑の直前に国王が崩御したため、かろうじて生き 延びた。
1547年1月、持病の梅毒が悪化したヘンリー8世は56才で死去。
代わって9才のエドワード6世が即位した。その摂政として、伯父のサマセッ ト公爵、エドワード・シーモア護国卿が権力を握る。彼は、エドワードの実母 ジェーン・シーモアの兄だった。
寡婦となったキャサリン・パーは元の恋人、海軍卿トーマス・シーモアと 再婚。エリザベス王女を引き取ったが、夫は幼い王女に手を出してしまう。
1548年キャサリン・パーの出産と産褥熱による死。36才だった。トーマス・ シーモアは15才のエリザベス王女との結婚を画策。1549年トーマスは謀反人と して処刑された。
1551年頃アンナは、弟ヴィルヘルム5世への手紙に帰国への希望をしきりに 漏らす。
1552年エドワード・シーモア護国卿処刑。
アンナは弟への手紙に「一体次に何が起こるやら」と書いている。
アンナの管理する広大な不動産には、リッチモンド宮殿、以前ブーリン家の 所有だったヒーヴァー城、ダートフォード宮殿、ペンズハースト宮殿、さらに チェルシー・マナーの宮殿があった。
彼女は金と召使のことで頭が一杯でこうも漏らしている。「それにこの国で は何をするにもお金がかかり、家政をどうやって切り盛りしたらいいのか分か りません」
1553年7月6日、第3代国王エドワード6世が15才で夭折。死因は父ヘンリー8 世譲りの先天性梅毒だった。
王位継承第三位だったジェーン・グレーがウォリック伯ジョン・ダドリーに よって担ぎ出され、第4代国王として即位。ジェーンの9日天下と処刑。
同年9月30日第5代国王メアリー1世即位。アンナはエリザベスと共に戴冠式 に出席した。
イギリス最初の女王となったメアリーは、亡き母キャサリン・オブ・アラ ゴンの遺志を継いでカトリックを一時的に復活させ、その裏でプロテスタント の粛清を行った。“ブラッディー・マリー”と呼ばれる由縁である。
1554年メアリー1世は、スペインの皇太子と結婚。夫は2年後スペイン国王 フェリペ2世として即位した。
アンナの手紙には、「イングランドはイングランド。私たちはよそ者なので す」というつぶやきが垣間見える。
1557年、ようやくと病を得たアンナ・フォン・クレーフェは、7月16日に死 去。42才の生涯だった。
最初の6ヶ月を王妃として、そのあと17年の長きを王の妹として、不慣れな 異国暮らしに耐えた。ヘンリー8世の死後10年、6人の妻たちの中では最後まで 生きた。
記録には、良き家政の守り手にして召使には寛大であったと伝わる。
その遺言の中に記された長い遺贈品のリストには、侍従、女官、馬番から洗 濯女にいたるまで、全員が名前入りで記されている。領地の貧者たちにも配慮 が示された。
心やさしきアンナは、ヘンリーの妻たちの中ではただ一人、ウェストミンス ター寺院に埋葬されている。
翌1558年11月、メアリー1世の死去に伴い、アンナが可愛がっていた少女は 第6代国王エリザベス1世として25才で即位。名君として45年に渡りイギリス を統治した後、ステュアート朝に引き継いだ。
◆◆【4】作者ハンス・ホルバイン(1498-1543)について ◆◆
ハンス・ホルバインはドイツの画家・デザイナーである。
ヨーロッパ絵画史上最高の肖像画家の一人であり、イギリス国王ヘンリー8 世とその周辺で制作された一連の肖像画作品は、150点にも達する。
それらの特徴は徹底したリアリズム描写であり、同時に歴史的な記録として も名声を不動のものとした。
画家としては、チョークによる素描、水彩画、テンペラ画、油彩画、そして 版画、書物の挿絵・図案、ミニアチュール(細密画)、壁面装飾としてのフレ スコ画、教会のステンドグラス製作等、あらゆる絵画技術に通暁している。
加えて、250枚にも上る金銀食器、宝飾、バッジ、ブローチ、ボタン、バック ル、大礼用のローブから、儀式用の出し物、武具、馬具にいたるまであらゆる 種類のデッサンを残している。
彼は、著名な画家であり卓越した素描家だった同名の父ハンス・ホルバイン (大ホルバインと呼ばれる)、伯父ジグムント・ホルバイン、兄アンブロジウ ス・ホルバインという画家一家に生まれた。
故郷であるドイツ・アウグスブルクの父の工房で修行を始め、次いで学芸の 盛んなスイスのバーゼルに移り、同地の画家ハンス・ヘルペストの下で修行を 終えた。
バーゼルを中心に前半生において制作された肖像画や宗教画にはイタリア・ ルネサンスの影響が強く見られ、ロンドンにおける後半生で制作された一連の 肖像画にはフランドルやフランスの影響が顕著である。
私生活においては、22才頃に結婚した年上の寡婦エルスベート・ビンツェン シュトックとの間に二男二女をもうけたが、次第に不仲となり、1532年の第2 次イギリス滞在以後はロンドンにて別の家庭を築くと二人の子を残した。
1543年、10月ロンドンで流行していたペストに倒れる。直前に書かれた遺言 には、バーゼルに戻る心積もりであったことが伺える。45才、まさに画家とし て油の乗り切った時期での惜しまれる死だった。
王侯貴族、政治家、文化人、商人などパトロンとなった人物も多岐に渡る。
ルネサンス最大の人文主義者のエラスムスや、イギリスの人文主義者・政治 家のトーマス・モアとの友情の上に生まれた肖像画作品群は、歴史的遺産とし ても特筆される。
宗教改革の真っ只中に生き、偶像破壊の波に翻弄されながらも、活動場所を 求めて遍歴を続けたその姿は胸を打つものがある。
◆◆【5】肖像画の内容について◆◆
婚礼の衣装を身にまとった、ヘンリー8世の花嫁候補アンナ・フォン・クレ ーフェ24才の肖像である。
真紅のベルベットのドレスは胸元と袖口、裾下が金襴で縁取られ、その上に 真珠がふんだんに縫い付けられている。ベルトや腕バンドも同様に統一された デザインである。
真珠の縁取りの金襴の刺繍のあるヘアバンド。被り物は金糸だけで編まれ、 宝石の房が垂れ下がる。
そして十字架のブローチに金の管を繋いだネックレス。
目も綾な贅沢な衣装である一方、参考図版のジェーン・シーモア他の清新な 英国式デザインと比べると一時代前の古めかしさを感じさせる。
その袖口と胸元に覗く白い衣装も、古いニスが黄変した結果、純白に見えな いのがもどかしい。
地理的にも経済的にも、後進国ドイツの王女の装いなのである。
ホルベインは王女アンナを真正面から描いた。デンマークのクリスティーナ の顔もほぼ正面向きであるのでこれは王の注文であったろうし、見合い写真に ふさわしいものである。
彼は真紅の衣装に身を包んだ王女を目にしたとき、さかのぼる十数年前フラ ンスに滞在した折に、熱心に観察したジャン・フーケの作品「勝利王シャルル 7世の肖像」を思い浮かべたに違いない。
⇒ https://www.shouzou.com/mag/p15.html
シャルルは深い緑の背景の前に、深紅の出で立ちで描かれていた。ホルバイ ンはこれにならって、背景をドレスの色の補色である緑で塗り込んでいる。
緑に赤という補色対比は最もインパクトのある色相対比である。
それでいて赤と緑は明度がほぼ等しく低いために、画面から後退し、反対に 明度の高い顔や手・胸元を前方に押し出す役目を担っている。
さらに両袖口の金襴の縫い取りは、画面下の両脇から視線を上へと誘導して 美しい頭部へと至らせる三角構図を形作っている。
こうした手法は見る者(注文者ヘンリー8世)に対して、強い印象を引き起 こさずにはおかないだろう。
ホルベインは自らの声をそっと画面に塗り込んでいる。
事実、画家にとって、母国語で話すことのできるこのアンナ王女と妹のアメ リア王女の肖像画制作は、打ち解けた雰囲気の中で行われた。
クリスティーナ王女のときなど、対面制作はきっかり3時間と限定されてお り、最初から拒否されているようなものだった。
しかし、今回ばかりは時間的制約に縛られてはいなかったようである。 クレーフェ公国側から持ち込んだ縁談でもあり、宮廷人が興味深く見守る中 での制作であったけれども、NOであるはずはなかった。
こうして、地味な性格のおっとりしたアンナ王女は、辛抱強く退屈な不動の ポーズを務め上げた。
彼女の眼差しは、鑑賞者の方を向いているのだが、焦点が合っている様で合 っていない。それは、こちらを見続けるのに疲れて、自分の世界に入り込んで いることを思わせる。
「アンナ・オブ・クレーフェは美しくなかった。美人という報告は外交官が都合のよいように誇張したものだった。(中略)
ホルベインは慣習に従い正面から描いているが現代的な感覚ではそれ程ひどいとは思えない。広い額、離れた両目に厚ぼったいまぶた、そしてとがった顎。」
アントニア・フレーザー
「奇妙なほど生気のない左右対称な顔立ち」
ヘレン・ランドン
どうも現代人のアンナの容貌に対する評価は辛口である。
筆者の見るところ、アンナの顔立ちは気品があり、十分美しい。その表情か らは慎み深さ、忍耐強さ、そして芯の強さを感じさせるのだが、それはそのま ま描いた画家が感じた印象に違いないのだ。
注文主の国王ヘンリー8世もこの肖像画には好印象だったのであり、それゆ えにこの結婚が成立したわけである。
ただし巨匠ハンス・ホルバインをもってしても、見落としていた重大な一点 があった。
アンナの鼻は随分高かったようなのだ。これは正面から見た肖像ではほとん ど分からない。
鼻が高いというのは、平面顔のアジア人にとっては美を意味するが、西洋人 にとってはそうではないようだ。西洋で最も鼻の高いのは、嫌らしい魔女であ り、これを彼らは連想するらしい。
アンナ像の参考図版を2枚掲載したので見ていただきたいのだが、後年描かれ た右図では確かにその鼻は高い。
おそらくお見合い用にクレーフェ公国側から、イギリス側に提出されたもの であろうと推測される左の図は、鼻は低く修正されているように思われる。
〈参考文献〉
「ヘンリー8世の六人の妃」アントーニア・フレイザー著 森野聡子・森野和弥訳(創元社)1999年
「ヘンリ8世の迷宮―イギリスのルネサンス君主」指昭博編(昭和堂)2012年
「英国王と愛人たち―英国王室夜話」森護著(河出書房新社)1991年
「図説エリザベス一世 」石井美樹子著(河出書房新社 ふくろうの本)2012年
「ホルバインの生涯」海津忠雄著(多賀出版)1989年
「アートライブラリー ホルバイン」ヘレン・ランドン著 保井亜弓訳 (西村書店)1997年
「世界大百科事典」(平凡社)
"TOUT L'OEUVRE PAINT DE HOLBEIN LE JEUNE, Les Classiques de l'Art" PIERRE VAISSE, HANS WERNER GROHN著(Flammarion)1972年
"The New Encyclopedia Britanica"
◆◆【6】次号予告◆◆
チューダー朝後期のエリザベス1世の時代は、日本の安土・桃山時代に当た ります。
織田信長とエリザベス1世は一つ違いでしたが、性格的には、癇癪持ちの父 ヘンリー8世が信長に似ているようです。
9日天下の傀儡ジェーン・グレーを明智光秀に例えれば、血生臭いメアリー 1世は晩年の豊臣秀吉でしょう。
メアリーが病死したのは、戦争でフランス国内の最後の領土カレーを失った 直後でしたし、秀吉は無謀な朝鮮侵略の最中に病死しました。
そして苦労の末に天下人となり、太平の世を築いたのがエリザベス1世と徳 川家康という役どころです。
昨年のロンドン・オリンピックでは、ロンドン塔の映像が紹介されていまし た。イギリスの歴史といえば必ず登場するのがロンドン塔です。
ふと思い立って夏目漱石の『倫敦塔』を再読してみたのですが、これがなか なかに興味深いのです。
末尾に引用されている英文、W・H・エインズワース作“断頭吏の歌”を紹 介します。首斬り役が斧の刃を研ぎながら、その日の仕事を歌います。
斧は尖って鉛並みに重いさ、項(うなじ)に触れるや首が飛ぶ。
シュル、シュル、シュル、シュル。
王妃のアンが喉元晒(さら)し、運命(さだめ)の一振りじつと待つ。
剣(つるぎ)は頚(くび)を一刀両断、そりや瞬きの間だから痛くない。
シュル、シュル、シュル、シュル。
ソールズベリー伯の奥方は死なず、貴人の誇りと気品の儘(まま)に。
振り上げし斧が頭(こうべ)を割れば、欠けたる刃先はなまくらに。
シュル、シュル、シュル、シュル。
キャサリン・ハワード王妃が云うのさ、金鎖あげるから楽に逝かせて。
それが無駄ではなかつた訳よ、首に触れるや飛んだゆえ。
シュル、シュル、シュル、シュル。
青ひげ公・ヘンリー8世の犠牲者の名前が連なり、どうにも面白いので敢え て日本語に置き換えてみたのです。
いわずもがなではありますが、やはり漱石はとんでもなく上手でした。他 にも賢治、敦に梁歩、桑田佳祐の名が脳裏をかすめ、臓腑を病むほどの刻苦 なくして美文はならず。ささやかですけれども、そんな気がしたものです。
16世紀のイギリス史をざっと俯瞰し、「倫敦塔」を読んでみると一興です。
次号も引き続きハンス・ホルバインの肖像画を紹介します。
画家は当代隋一の思想家や作家を友としていました。中でも白眉といえるの がエラスムスとトーマス・モアです。
エラスムスの『愚神礼賛』、トーマス・モアの『ユートピア』はその名を知 らぬもののない名著であり、刊行から500年になるというのに多くの知識人に 影響を与え続けて来ました。
特にヘンリー8世に大逆罪で処刑されたトーマス・モアは20世紀になってか ら殉教者として列聖されていますし、マルクス主義者からは「近代社会主義の 父」と呼ばれているのです。
ホルバインは二人の肖像画を描いています。20代で描いたエラスムスは詩的 に、30代で描いたトーマス・モアはそこに剛毅の塊が存在するかのようながち がちのリアリズムで。
次回は「トーマス・モアの肖像」をメインに、「エラスムスの肖像」も併せ て紹介したいと考えています。またホルバインの生涯について次号ではこの二 人との出会いを含めて語る予定です。
何卒ご購読のほどよろしくお願いたします。
【まぐまぐ!】『時空を超えて~歴代肖像画1千年』発行周期:不定期
登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000217722.html
Copyright (C) 2020 SHOUZOU.COM. All Rights Reserved.
《このメールマガジンの内容を無断で転載掲示することを禁じます。ただし、リンクやお友達への転送はご自由です。》